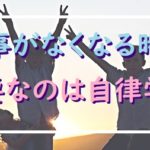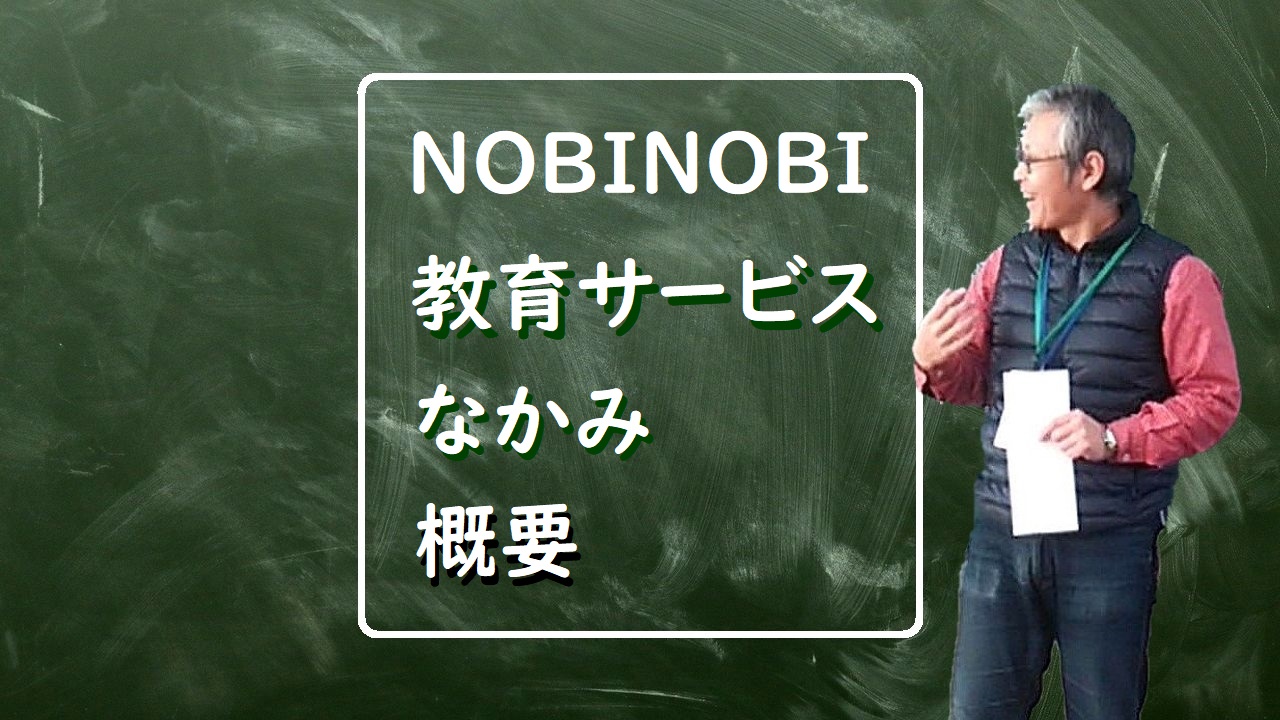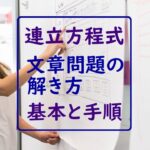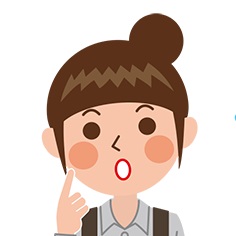
何がどう違うの?

記事の内容は
●「自立」とは、他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと
●「自律学習」とは、小学生、中学生、高校生の目標となる学習の姿勢
●「自立学習」とは、ひとりだちするための勉強全般
●まとめ まず必要な学習は……
こちらの記事を書かせて頂いたのは、

●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。
●年評定平均:中学時代3点台→高校進学後4.9、4.8、4.4の塾生を輩出。
●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学(在学中)。
●オリジナル直筆記事が、グーグル3ワード検索で1位(2024.5.1現在)
●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」
で、2020年6月から36ヶ月以上ランキング1位。
2020年3月開設15ヵ月目で月間4万PV超。
●元公立高校教員
●現役カウンセラー

疑問解消の
お役に立てれば
幸いです。
目次【タップでジャンプ】
“自律”と“自立”の意味の違いは?
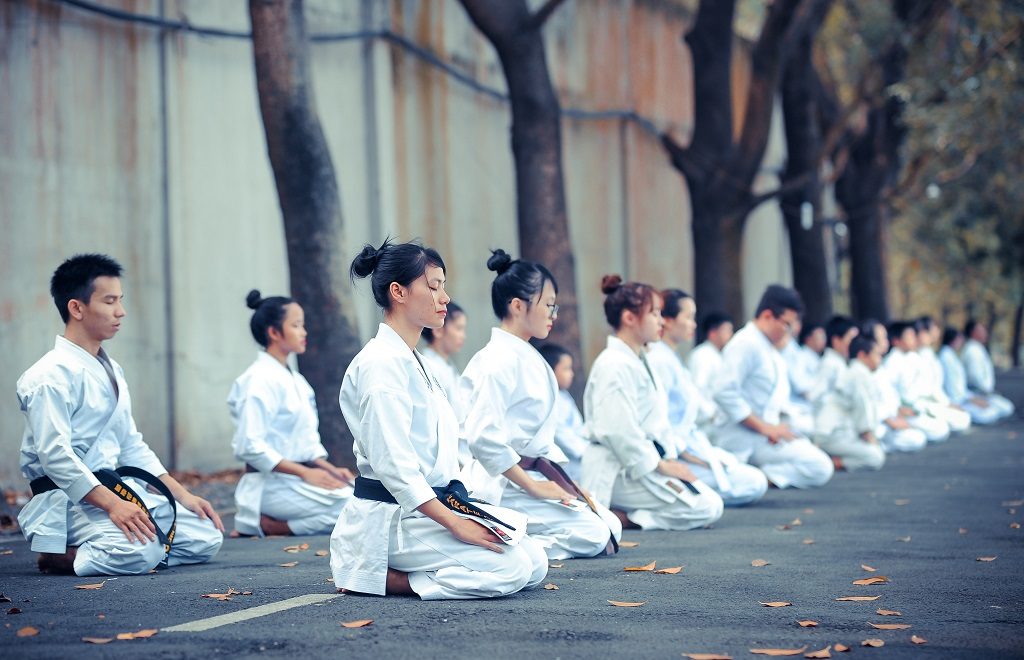
学校の教育目標で謳われる
「自主、自律の精神」の
“自律”。
一般的に「○○的自立」という
使われ方をする“自立”。
両方とも“じりつ”と読みますので、

変わらないでしょ!
と使われている場合が
多いように感じます。
ですが、実は
ハッキリした違いがある
のです。
“自律”とは?
「自律」とは、どんな状態を指すのでしょうか?
無料のウェブ百科事典
“コトバンク”によりますと、
1 .他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動すること。⇔他律。
2 .カントの道徳哲学で、感性の自然的欲望などに拘束されず、自らの意志によって普遍的道徳法則を立て、これに従うこと。⇔他律。出典:デジタル大辞泉(小学館)
1.他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。
「学問の-性」
2.[哲] 〔ドイツ Autonomie〕 カント倫理学の中心概念。自己の欲望や他者の命令に依存せず、自らの意志で客観的な道徳法則を立ててこれに従うこと。
同音語の「自立」は他の助けや支配なしに一人で物事を行うことであるが、
それに対して「自律」は自分の立てた規律に従って自らの行いを規制することをいう。出典:大辞林 第三版(三省堂)
1. 自分で自分の行ないを規制すること。外部からの力にしばられないで、自分の立てた規範に従って行動すること。
※学校教育法(1947)一八
2.カントの倫理学の根本原理の一つ。実践理性が、欲望に動かされることなく、みずから普遍的道徳法則を立て、それによって自分の意志を規定すること。出典:精選版 日本国語大辞典(小学館)
個人が他者の統制にしばられずにみずからの規範,準則,目的といった規準を定立し,みずからの意見がみずからの行為を律する余地があるとき,そこに個人の自律ないし(または)自治があるという。
出典:世界大百科事典(平凡社)内「自律の言及【自治】」より
また、学校教育法によりますと、
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)(抄)
第二章 小学校
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
と記載されています。
“自律”は、教育の分野では、
学校教育法でも使われている
なじみ深い言葉。
“自律”を使った言葉で
他によく目にするのは、
“自律神経”や“自律型ロボット”
などの使い方。

“自動お掃除ロボット”は、
身近な自律型ロボットの
代表です。
自律型ロボットとは、
おおまかにはコントローラーの無いロボットのことです。
日々の生活の中で一番身近な自律型ロボットは、自動お掃除ロボットです。
ご存知のように自動お掃除ロボットは、さまざまなセンサーなどで、家具などを回避しながら掃除をし、充電が切れそうになったら自動で充電をします。
このように人間は操作せず、ロボット自身が判断をして動くロボットのことを指します。
と説明されています。
哲学者カントさんの考えは
一旦脇において
“自律”をひらたく言いかえると、
とも言えます。
“自律”の反対は“他律”。
コントローラーがないと動かない、
指示命令がないと動けない、
そんな状態をさす言葉と
言えそうです。
“自立”とは?
一方“自立”とは、どんな状態
でしょうか?
再び「コトバンク」によりますと、
他への従属から離れて独り立ちすること。他からの支配や助力を受けずに、存在すること。
「精神的に-する」出典:デジタル大辞泉(小学館)
他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと。
ひとりだち。独立。 「親もとを離れて-する」出典:大辞林 第三版(三省堂)
他への従属から離れてひとりだちすること。一本立ち。
出典:精選版 日本国語大辞典(小学館)
と説明されています。
“自立”は、
今から2100年ほど前の中国
前漢の時代に編纂された歴史書
「史記」の「伍子胥列伝」で
「呉王僚を刺さしめて自立す。」
という一節でもすでに出てきていて、
「自分で帝王の位につくこと。」
ちょっと物騒な意味で
使われています。
キャリア教育の世界で
“自立”といえば
仕事(技能)の自立
(自分で考えて業務ができること)
経済面での自立
精神的な自立
身体的自立
の4つあるとされています。
使い方としては
“自立支援”や
“自立歩行ロボット”
が挙げられます。
ロボット工学系専門学校の
ホームページでは、
“自立歩行”=“二足歩行”と
表記されていました。
“自立”とは、
他の助けや支配なしに
自分一人の力だけで
物事を行うこと、
状態のことを表している
と言えそうです。
では“自立”の反対は何でしょうか?
“孤立”と表現する方もいらっしゃいますが、
一般的には“依存”。
自立は英語で“in-dependent”、
直訳すれば“非依存”
となります。
自分の足(能力)では立っていられない、
そんな状態をさす言葉と
言えそうです。
自立と依存の関係につきましては、
ご自身も障害をお持ちで、
障害を持つ方の視点で捉えた
小児科医で
東京大学先端科学技術研究センター准教授の
熊谷晋一郎(くまがやしんいちろう)先生
のこちらのインタビュー記事をご参照ください。
自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと
AD
“自律学習”と“自立学習”の違いは?

このように言葉の歴史や
使い方から見てくると、
“自律学習”と
“自立学習”の違いも
はっきりしてくる
と思えるのです。
“自律学習”とは?
筆者の私見も含めて
ザックリ表現すると、
“自律学習”とは、
学校教育法にも出てくる
教育の分野では一般的な表現で、
勉強だけでなく、
部活動、委員会活動、習い事、
家の手伝いでも、
どんな学びでも
100%といかないまでも
やると決めたことは
しっかり取り組める状態
そんな学習姿勢を指す言葉
といえるのではないでしょうか。
どちらかというと、

目標となる“学習”の姿
と言えそうです。
“自立学習”とは?
では“自立学習”は
どうでしょうか?
深読みしすぎかもしれませんが、
筆者は、
“自立のための学習”
=“自立を手にするための学習”
の意味を
読み取ってしまいます。
例えば、
就職をひかえた高校生、
大学、短大、専門学校の学生さんたちなど、
と、とらえられる
と思うのです。
どちらかというと
キャリア教育の世界で
使われる言葉
という印象が強いのです。
“自律学習”が教育の場で使われるわけ まとめ

こちらの記事では、
●「自立」とは、他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと
●「自律学習」とは、小学生、中学生、高校生の目標となる学習の姿勢
●「自立学習」とは、ひとりだちするための勉強全般
筆者も含め、
教育にたずさわる者にとっては
“自律学習”も“自立学習”も
どちらも大切な考え方です。
ただ
まず初めに身につけるべき
学習姿勢とは、
お母さん、お父さん、先生や塾講師…
指導者が1から10まで
手取り足取り面倒を見なくても、
自分を自分で
コントロールしつつ
勉強できる“自律学習”
ではないでしょうか。
これが身につかなければ、
社会にでて自分で
自分を支えられる
“自立”した状態を
手にいれることは
難しくなってしまう
と思うのです。
わざわざ教育法の条文で
使われているのも、
そんな想いや願いが
込められているのでは…
と考えています。
些細なことかもしれませんが、
こういったことまで
強く意識して
生徒さん一人一人の
“自ら学ぶ力”
を引き出したい!
“自律学習”を身につけて、
そして
将来の自立に向けた
お手伝いを
続けていきたい…
そう考え、
日々の取り組みに
活かしているところです。

ありがとうございました。
少しでもお役に立てれば幸いです。
こちらの記事をご参照ください。
教室の取り組みにつきましては、下記の記事をご参照ください。