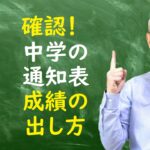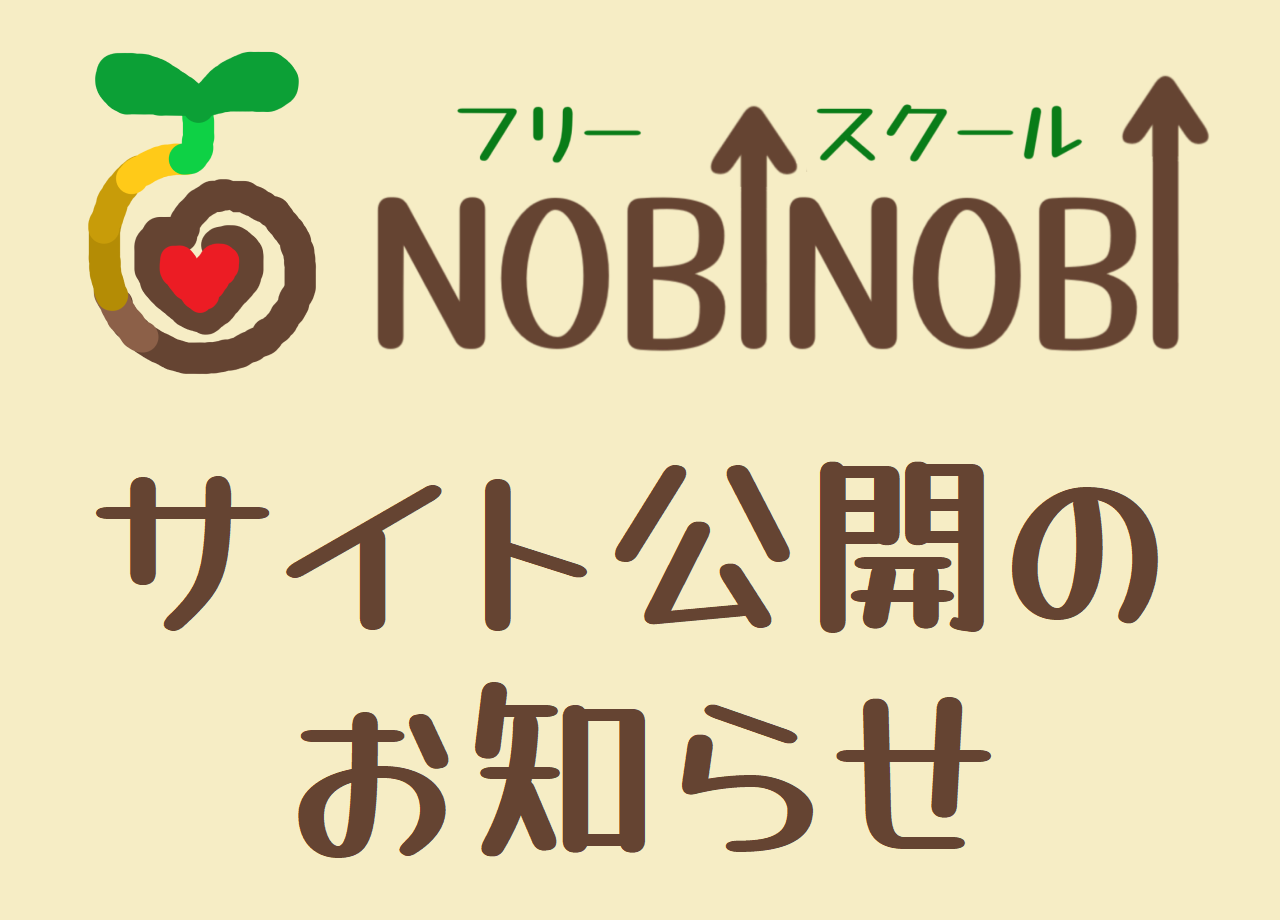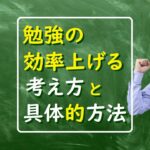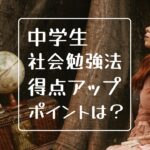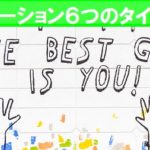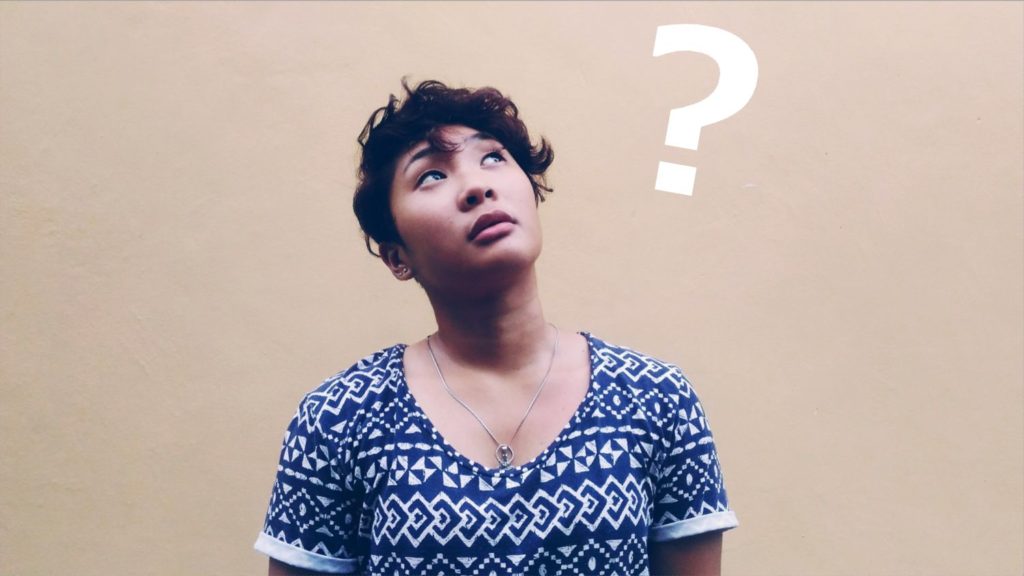
中学の教科の成績=“評定”は5段階、決め方のポイントは?
こちらの記事では、

スクールNOBINOBIが
中学校5段階成績(評定)の出し方について、
新潟市内の中学校と
文部科学省、
東京都教育委員会の公開資料をもとに、
大切なポイントを説明します。
オリジナルの
わかりやすい図表もご用意
しました。
記事の内容
●中学校の成績(評定)の出し方にはルールがある。
●“内申点”とは、5段階の成績(評定)の合計のこと。
●“内申点”は、高校入試で合格不合格を決める重要な材料。
●“内申点”をあげることは、希望高校進学への近道。
記事を書いているのは、

●小中学生対象完全個別指導塾の校長(経営者兼専任講師)
●開校5年半で、新潟県内トップ私立高校合格者を輩出。
●年評定平均:中学時代3点台→高校進学後4.9、4.8、4.4の塾生を輩出。
●サポートした不登校の卒塾生、大学へ進学。
●オリジナル直筆記事が、グーグル2ワード検索で1位(2024.4.1現在)
●当ブログ、にほんブログ村カテゴリー「中学受験(個人塾)」
で、2020年6月から36ヶ月以上ランキング1位。
2020年3月開設15ヵ月目で月間4万PV超。
●元公立高校教員
●現役カウンセラー
こと“のびのび”。

目次【タップでジャンプ】
どうやって決めてる?中学校の各教科の成績

小学校とは違う、
中学の各教科の
成績(評定)の決め方とポイントを、
新潟市の中学校を例にお話しします。
はじめにおさらいしておきましょう。
中学校各教科の評定(成績)の出し方
小学校では、
児童の皆さんが先生から渡される
通知表に書かれている
成績=“評定”は、3段階
でした。これが
中学校になると
教科ごとの成績は5段階 に。
3段階から5段階へ
成績の出し方が変わることで、
成績=評定を出すための
評価の方法も変わる
のです。
成績=評定の出し方の確認が必要なわけ
新潟市の
中学生の成績
は、通知表の
のです。
この成績の合計を
内申点
と言います。
●3年の成績のみを内申点とする都道府県がある
など、お住いの都道府県によって中学時代の成績=内申点の出し方は変わります。
例えば、
3年間の学年評定(成績)を
合計して点数化する
新潟市の場合、
9教科の評定が 1年、2年、3年全て“5”でしたら、
3年×9教科×評定5=135点
になり、
中学校の内申点の“満点”は、
オール5=135点。
この評定の合計
“内申点”(=学習の記録)は、
高校入試で合否を決める材料の一つ、
試験会場に入る前に決まる持ち点
になるのです。
新潟県の高校入試の合否は、
“学力検査(一般入試1日目)”
中学校の成績=“内申点”
“学校独自検査(一般入試2日目)”
※令和6(2024)年度の全日制一般入試での実施は、中央高校音楽科1学科のみ
で決められます。
ですから、評定の合計
なのです。
生徒さん本人だけでなく
ご家庭でも
今一度確認して頂きたい
ポイントです。
次に、

決まるまでの流れを
見ていきます。
学期の各教科の成績=評定が決まるまで
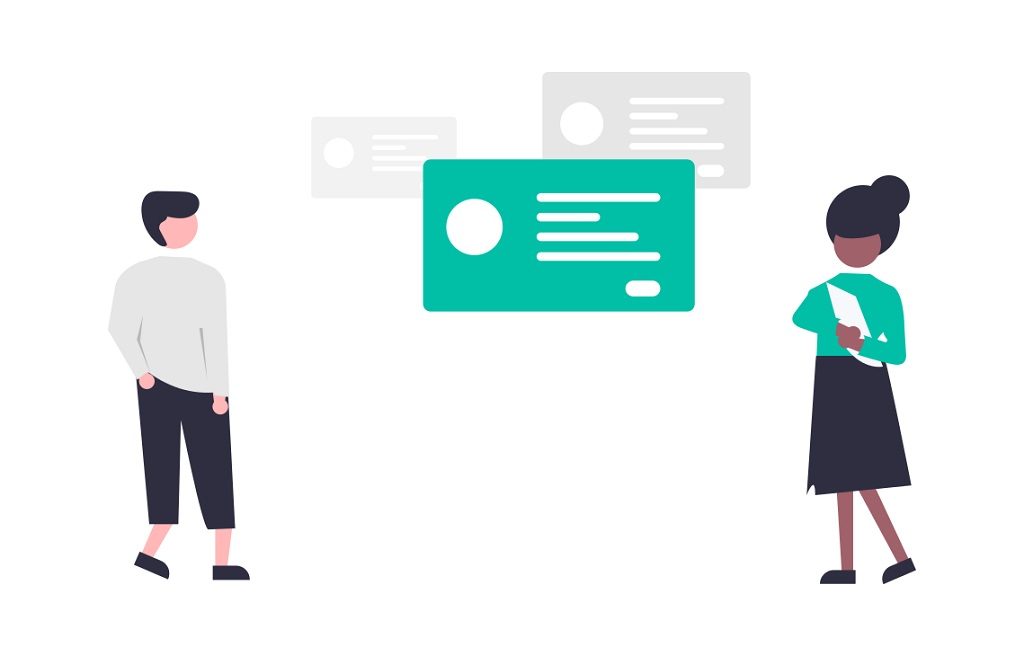 では、この大切な内申点のもとになる
では、この大切な内申点のもとになる
5段階の成績=“評定”
はどのように決める
のでしょうか?
表で確認!学期ごとの各教科の評定(成績)の出し方
旧学習指導要領をもとに
作成した
オリジナルの表です。
【中学校の学期ごとの評定(成績)の出し方】

※転載をおひかえ頂き、ありがとうございます。
※2021年度からの学習指導要領は、 図中の観点が3つになりました。
以下のページをご参照ください。
文部科学省-平成29・30年改訂 学習指導要領、解説等-学習指導要領改訂に関するスケジュールと学習指導要領の広報について
ここでは
旧学習指導要領をもとに
作成した上の表で
学期ごとの教科の成績=評定が決まるまでの流れ
を見ていきます。
学期ごとの各教科の評定を出す、大まかな流れ

“4”です。
と先生が通知表に評定を書き込むには、
評定“4”を付ける材料である
“評価”を決める必要が
あります。
この“評価”は、
評価の基準=“観点”ごとにつけられるため、
“観点別評価”と言ったりします。
各教科にある
“観点”(2021年度からは3つ)
ごとに“評価”していく
のです。
この“評価”は、
大雑把な表現をさせて頂くと
A ≒ 良い 、B ≒ ふつう 、C ≒ 悪い の3段階
で付けられます。
2020年度までの旧学習指導要領では
この“観点”は、国語の場合5つ
ありました。
よく耳にする
代表的な評価の“観点”には、
書く力≒文章力
読む力≒読解力
があります。この
国語を例に教科の評価から評定までの流れ
を順に見ていきます。
観点ごとの評価を、評定(成績)に変えるには?
まずはじめに、国語の
のです。
観点①「国語への関心・意欲・態度」はどうか → A
観点②「話す・聞く能力」はどうか → A
観点③「書く能力」はどうか → A
観点④「読む能力」はどうか → A
観点⑤「言語についての知識・理解・技能」はどうか → A
次に、この
ことになります。 上の例で、
5つの観点すべての評価が「A」でしたので
今学期の「国語」の評定:“4”。
おおまかですが、こんな流れです。

評定は“5”になると思った……

●「知識・技能」
●「思考・判断・表現」
●「主体的に学習に取り組む態度」
の3つの観点。
それぞれの観点を原則
≒ 良い
B:「おおむね満足できる」状況と判断される
≒ ふつう
C:「努力を要する」状況と判断される
≒ 悪い
の3段階で評価
しています。
評定の出し方は?5段階になる中学の成績 まとめ

こちらの記事では、
中学校各教科の5段階評定の出し方
について、
新潟市の中学校と
文部科学省、
東京都教育委員会の公開資料をもとに、
旧学習指導要領の基本の部分にしぼって
見てきました。
記事のポイントは
●中学校の成績(評定)の出し方にはルールがある。
●“内申点”とは、5段階の成績(評定)の合計のこと。
●“内申点”は、高校入試で合格不合格を決める重要な材料。
●“内申点”をあげることは、希望高校進学への近道。
の5点。
小学校とは大きく変わる
中学生の5段階の成績=評定の出し方をおさえておくことは、
評定の合計=中学時代の成績=“内申点”を高くして、公立でも私立でも高校入試を有利にする方法の一つ です。
くりかえしになりますが、
新潟市の場合は、
中学1年~中学3年までの
9教科の評定が
高校入試の“内申点”のベース
になります。
また、2021年度から全面実施となった学習指導要領では、
評定(成績)を付ける材料である“評価”を
決める評価=“観点”は
全ての教科で
3つになりました。

中3になってからで
いいや!
ではなく、 できるだけ早い段階から

成績アップできるかな?
と意識してもらう ことが、
希望高校進学への近道
といえるのではないでしょうか。

最後までお読み頂き、
ありがとうございました。
【関連記事】